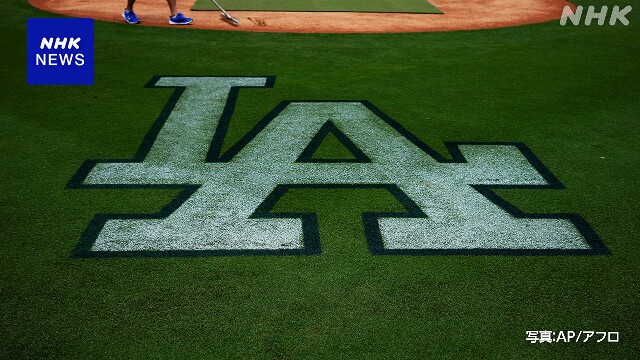夏の甲子園の頂点を象徴する深紅の大優勝旗。その旗を初めて茨城にもたらしたのが、1984年に出場した木内幸男監督(2020年死去)が率いた県立取手二高だ。
当時2年生だった桑田真澄、清原和博のKKコンビを擁するPL学園(大阪)との決勝を延長十回の末に破る。後に「木内マジック」の愛称で親しまれた名将の原点は、この年にあった――。
取手二の快進撃が始まったのは、この年の選抜大会からだった。メンバーの中心は、後にプロ野球へ進む主将の吉田剛(3年)や、エースの石田文樹(3年)=08年死去。特に石田は、1年生秋からエースとして木内が育て上げた逸材だった。
選抜に出場するのは2年連続だったが、前年は初戦敗退。夏は1981年を最後に全国の舞台に出ていなかった。
木内も吉田たちの3年目に賭けていたのか、「走攻守、本当に隙がないチームだった」。そう話すのは、84年の選抜に取手二とともに出場した県立明野高の監督だった浅野正勝(80)だ。
前年秋の県大会決勝で取手二と対戦。石田に0―4で完封された。続く関東大会でも、両校は決勝で対戦。この時は明野の左腕エースが奮闘したが、0―2で敗れていた。
木内からかけられたある一言
選手の能力の高さ以上に浅野が手ごわいと感じたのは、木内の勝ちへのこだわりと相手を侮らない姿勢だった。浅野が思い出すのは、木内からかけられた、ある一言だ。
84年の選抜出場が決まった年明けのこと。両校の出場を祝うため、木内と浅野を囲み、親しい間柄にあった他校の監督が会食の席を設けた。そこで木内から、こう頼まれた。
「選抜が始まる前にもう一度、練習試合をやってくれ」
木内は、試合には勝ったが、県大会と比べて関東大会で点差が縮まったことを気にしていた。
「うちが全国で勝ち上がるには、もっと左投手対策が必要だ。明野のエースを練習台にさせてくれ」
浅野は、選抜前にチームの調子が崩れるのを懸念し、木内の申し出を断った。「木内さんは子どもたちが勝つためなら、最良と思うことに力を尽くしていた。どんな相手からも学ぼうと、研究熱心だった」と振り返る。そうした木内の思いに応えるかのように、取手二は84年の選抜を勝ち上がっていった。
1回戦の松山商(愛媛)戦は、4―4の同点に追いつかれた直後の五回、1死満塁から吉田の適時打で突き放し、8―4で快勝。打線が粘り強さを見せた。
続く2回戦の徳島商戦は、右肩を痛めていたエースの石田がマウンドに上がる。終盤に2点を失ったものの4―2で勝利。投打で底力を見せた。
準々決勝で岩倉(東京)に3―4で敗れたが、春夏を通じて、木内にとっても、取手二にとっても、初めてとなる全国8強入りを果たした。
同じ年の甲子園出場監督という間柄を通じ、木内と仲を深めていった浅野には、木内の口癖が脳裏に焼き付いている。
「おれは職業監督だから、先生たちが教壇に立っている間も、どうしたら勝てるか考えている。先生たちには負けられないんだよなぁ」
木内は、浅野の12歳年上だった。土浦一高を卒業後、同校で野球部のコーチ、監督を務め、57年に取手二の監督に就任。学校教諭ではなく、当時、数少ない監督専任だった。
そして84年夏。初めて甲子園を制した木内の野球は、選手たちの個性を大胆に引き出す指導スタイルから「のびのび野球」と言われた。浅野は「学校の先生とは違う、一人の大人として、子どもたちと真剣に向きあったからこその指導方法だったのかもしれない」と話す。=敬称略(古庄暢)
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。